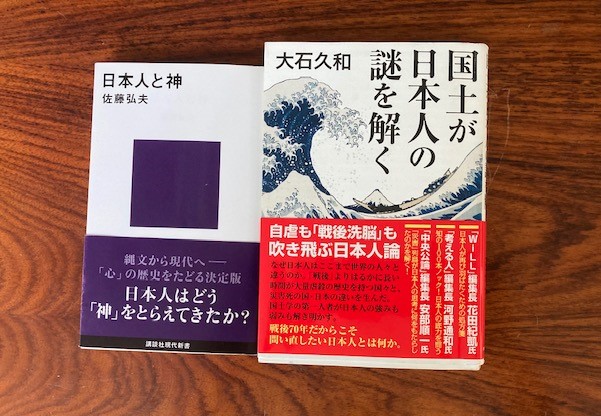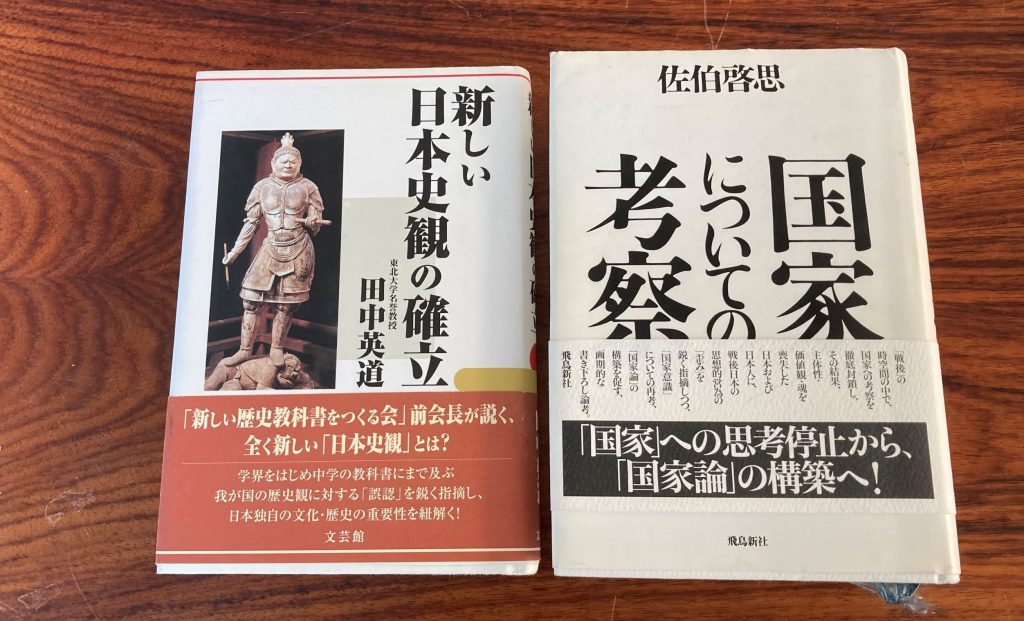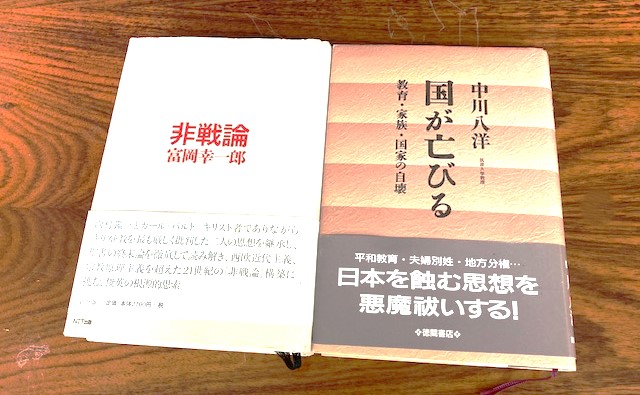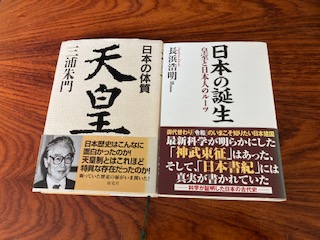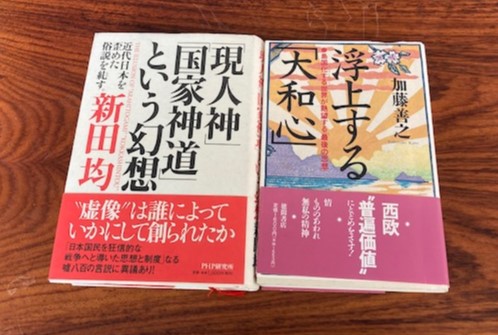
1 日本の文化と西洋の文明
日本は,四辺臨海の島国で他国と陸的に接することがない為に国家間での領土紛争は少なく自然環境の変動に因って生じる災害死が圧倒的であったのに対し,西洋では境界を接する国家間での領土紛争による戦争死が圧倒的とされます。日本の縄文や古墳の時代,人々は気候変動での災害死を悼み自然を動かす根源的で人智を超えるものを神々として畏れ敬い,神々への祈りの道具として土偶を作り,弥生末期頃からは大型の古墳を造り埴輪を並べました。ヤマト政権発祥の地である畿内では,古墳の高さや広さで権威と権力を誇示し,古墳では神々に対する祈りの祭典と祖霊への儀式を催し,権力者は人々の神々への尊崇と祖先崇拝の気持ちを纏めることで小王国となり,やがて小王国を統合するヤマト政権が誕生しました。ヤマト政権の頃,人々は自然の神々を畏れ敬い,和と共生を根本とする文化は新しい神も受け入れる土台を持っていました。
一方,ギリシアとローマを源とする西洋文明は,複数の民族を統合した国家が形成されて当初の多神教は否定され,自然を超越する根源の唯一神を絶対として(ユダヤ教・キリスト教・イスラム教),絶対神が信託した権力者は国家を統治する権限を持ち,人間の理性には限界はなく自然も制圧できる能力を有するとする合理主義思考の西洋文明が形成されました。
日本の文化が自然の中にも多くの神々を認めて「和をもって貴し」とする争いを避ける文化であったのに対して,西洋の文明は唯一絶対神の正義を旗印にして領土紛争や宗教戦争も厭わない文明だと思います。自然の中の神々を尊崇畏敬して春夏秋冬の自然のリズムの中で共生して命を繋ぎ,人間の理性には限界があるとする日本の文化と,唯一の絶対神の下で自然も制圧できるとする合理主義思考の西洋文明とは根本的な違いがあるのです。
2 日本国の統治と中華の文明
大陸の中で中国を中心とする中華文明の人々も陸続きで他族との領土紛争は絶えませんでしたが,人々はその救済を神にではなく絶対的な人の権力に求め,絶対的権力者となった皇帝は城壁都市を造り人々を囲い込んで人々を外敵から守りました。中華文明は皇帝の権力が絶対でしたが,人間の生き方や統治の在り方を説く道教や儒教が生まれ,さらにインド発祥の仏教も影響力を持ちました。
ヤマト政権は,草創期頃から道教や儒教を学び6世紀以降には仏教が導入されて大きな影響を受けましたが,7世紀に古事記や日本書記を創作し,万世一系の天皇の祖先を神(人格神)として権威の絶対化を図り,また滅ぼした人々の霊をも神と奉り恨みを閉じ込める為の大社も造りました。さらに,仏教文化と学問の殿堂として鎮護国家の仏寺を全国に創建しましたが,日本本来の自然の神々以外に人格神や仏を認める事は天皇の権威の源である祭祀権を弱めるものでした。ヤマト政権は,8世紀初頭に律令制度を整備して神祇官と太政官を設置し,神祇官は天皇の下での祖代からの自然神と祖霊への祈りの伝統的儀式を司り,統治権力の力で建造が進められた仏寺は鎮護国家を祈る祭場と学問の殿堂とされて人々の成仏が説かれ,後年には袈裟を纏って地獄に落ちることを畏れる天皇さえも現れました。
仏教の始祖である釈迦は,国家と家族を遺棄してまで人間の成仏を説いたとされますが,その後に広まった新仏教の思想的影響は大きく神仏融合の考えも広まった為に神が本源か仏が本源か混沌し,さらに人々は彼岸浄土での成仏から現世での成仏さえも願うようになり草木国土悉皆成仏の思想も広まりました。ヤマト政権は,中華文明の影響を神と仏を融合させて独自の飛鳥・白鷗・天平の文化を作りましたが,天皇による自然の神々の儀式と万世一系の祖先に対する祈りは天皇家だけの秘事的儀式となり,天皇の祭祀権は人々から遠くなりました。その結果,天皇の祭祀権威が人々から見えなくなって現在に至りますが,中華文明の影響は日本民族の精神を揺るがすまでには至らず,日本に溶け込んだ儒教は統治原理と人格陶冶の学問として江戸幕藩体制の下で治国の法ともなりましたが日本固有の国学も生まれて伝統文化を壊すには至りませんでした。
3 日本の文化と欧米の文明
日本は,ヤマト政権による創国から江戸幕藩体制までの間,自給自足の基盤として列島内の限られた資源を分け合う分度の文化を持つ国家であり,欧米の文明に見られるように正義を旗印として他国の資源を奪う文化ではありませんでした。ところが文明開化を叫ばれた明治期に,日本政府は,西洋型の国家を近代国家建設の手本とし,恐慌や人口問題もあって弱肉強食の帝国主義と合理主義を受け入れ,農業を基盤とする国家から工業を基盤とする国家への転換を計り,その為に石油石炭の化石燃料等が必要となってこれらを海外資源に頼り,さらに先進列強に肩を並べようとして国家国民挙げて海外進出の機運が高まり,遂にはエネルギー資源の確保と海外権益を保護することを名目として第二次世界大戦を戦うことになり,その結果,日本国民は悲惨残酷な戦争の地獄を体験しました。
大戦の勝利国であるアメリカは,日本を占領下に置いて日本の伝統的思想の根本を否定し,欧米的合理主義を基とする自由と人権の思想を徹底的に浸透させて,その主導下で現在の日本国憲法が作られましたが,現行憲法は,「象徴」の名目で天皇の伝統権威を葬り去り,個人の尊厳を根本価値に置くことで日本民族の伝統的同一性を曖昧にし,日本独自の集団主義を否定して個人主義への転換が計られました。日本人は,有史来の初めての経験である占領下の被支配民族となり,その敗戦ショックにより侵略戦争史観(自虐史観)を広く受け入れ,個人の尊厳を憲法の根本価値とする自由と平等の人権意識と絶対的平和主義は,国民に圧倒的に受け入れられて現在に至っていますが,日本固有の伝統と文化の否定は民族の否定につながり,日本民族の統一的同一性を無くすものです。
日本人は,国家の統一性とは何か,日本民族とは何かを日本の創国時に立ち返って考える必要があるのだと思います。個人に人格的統一性が必要なように,国家には国家としての統一性がなければならないと思いますが,日本国の統一性は,ヤマト政権の創国から敗戦後の現在まで続く天皇の伝統的権威を中心とした日本民族固有の伝統と文化に求められるのです。
令和5年9月30日
立志学舎塾長 倉田榮喜